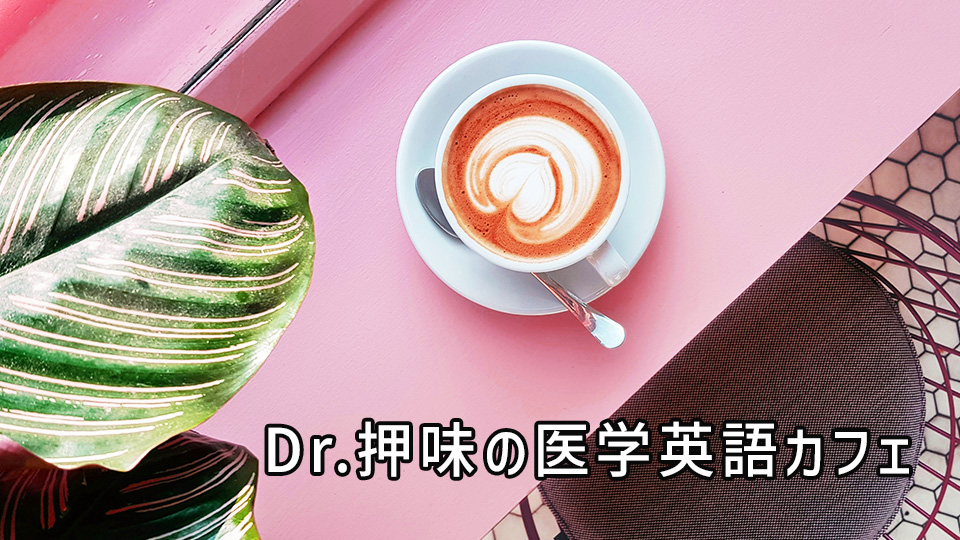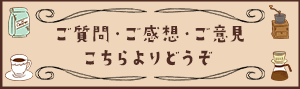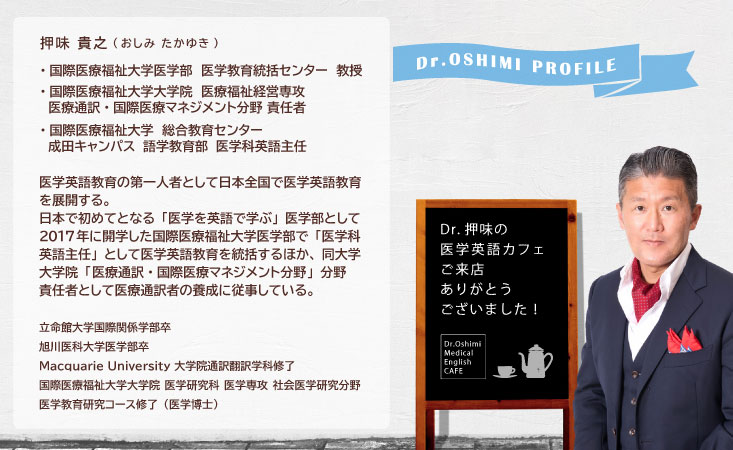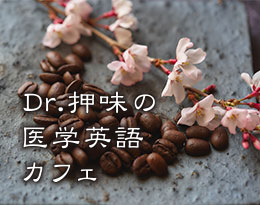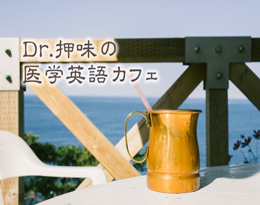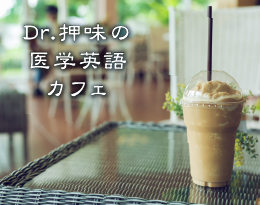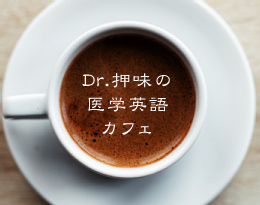こんにちは。「医学英語カフェ」にようこそ。
ここは「コーヒー1杯分」の時間で、医学英語にまつわる話を気軽に楽しんで頂くコーナーです。
本日のテーマは「インフォームド・コンセントで役に立つ英語表現」です。
外国人の患者さんに対して informed consent「インフォームド・コンセント」を得る際に、日本人の患者さんに対して普通に使っている表現をそのまま英語にして表現すると、手技や手術を拒否されるという場面が数多くあります。
そこで今月は外国人の患者さんも納得できるような「インフォームド・コンセントで役に立つ英語表現」をいくつかご紹介したいと思います。
なぜ「日本式の説明」では納得されないの?
informed consent「インフォームド・コンセント」とは、医療者が患者さんに治療や手術の内容、利点やリスク、代替手段などをわかりやすく説明し、患者さんが理解・納得した上で同意するプロセスのことを指し、以下の4つが基本要素とされています。
- • Disclosure「情報提供」患者にわかりやすく説明する
- • Understanding「理解」患者が説明を理解できていることを確認する
- • Voluntariness「自発性」患者が自由な意思で決定できる
- • Consent「同意」患者が納得して選ぶという意思表示をする
しかし日本と英語圏の医療現場では、これらの要素のとらえ方に違いがあります。
最も大きな違いがあるのは Disclosureです。
日本では「可能なリスクをすべて列挙する」ことが誠実であることとされ、「出血、感染、他の臓器への損傷、麻酔の際の問題、そして最悪の場合は死亡など、そういったリスクがあります。」のように、起こりうる問題を全て列挙する傾向にあります。
しかし英語圏では「頻度と重症度のバランスを踏まえて整理する」ことが求められるので、“Like with any surgery, there are risks such as bleeding or infection.” のような表現に留めることが一般的です。もちろん状況によっては日本のように全て列挙する場合もあるのですが、そのような場合でも必ず “We’ll take every precaution to keep you safe and support you through recovery.” のように安心感を与える表現も加えます。また “Most people do well after this type of surgery.”という表現も安心感を与える表現としてよく使われます。このような表現は日本では「雑」な印象を与えるかもしれませんが、英語圏の患者さんは医師に対してそのような安心感を与える表現を期待しているのです。
Understanding においても日本と英語圏では違いがあります。
日本では「わかりましたか?」という質問に患者さんが「はい」と回答すれば「患者は理解した」と認識されますが、英語圏では後述する teach-back method という手法が使われるのが一般的です。
また Voluntariness でも日本と英語圏では大きな違いがあります。
日本では「医師の推奨をそのまま受け入れる」のが自然とされがちですが、英語圏では「患者が自分の価値観や生活に基づいて自由に選ぶ」ということが前提であり、医師は選択肢を提示した後、患者の意思決定をサポートする立場に回ります。
そして最後の Consent に関しては、日本では署名をもらうことが同意の中心と考えられがちですが、英語圏では署名よりも「患者が納得して選んだ」ということを会話の中で確認する行為そのものが重視されます。よく英語圏の患者さんから日本の医師の bedside manner についての苦情を聞くことがあるのですが、その背景には英語圏の患者には「患者の納得感を得ることが診察の本質である」という前提があるのです。
このように informed consent の各要素の捉え方には違いがあるので、日本式のやり方をそのまま英語にして行なっても英語圏の患者さんはなかなか納得しないのです。
「病状の説明」で役に立つ英語表現
ではここから場面別で役に立つ英語表現をご紹介していきましょう。
場面に限らず、英語では signposting と呼ばれる transition として機能する表現が重要になります。ですから病状を説明する際にはまず “First, let me explain what’s happening in your body.” のような signposting を加えましょう。
病状の説明では、多くの日本人は下記のように病名から伝えてしまいがちです。
You have gastroesophageal reflux disease, or GERD for short. This is an inflammation of the lining of your food pipe caused by the reflux of stomach acid.
確かにこの説明では GERD という病気そのものはわかりやすく伝わるのですが、病名から説明すると患者さんは病名に圧倒され、その後に説明される病状も理解しづらいと感じてしまいます。
そこでお勧めするのが下記のような「型」です。
What’s happening is that (病態), and that’s why you’re having (患者の症状). This is called (病名), also known as (病名の一般名称).
この「型」を使えば下記のような「病状の説明」が可能です。
What’s happening is that acid from your stomach is flowing back into your esophagus, and that’s why you’re having heartburn. This is called gastroesophageal reflux disease, also known as acid reflux.
まずは身体の中でどのようなことが起こっているかに関する「病態」を説明し、その次に患者さんが実感できるように「患者の症状」との関連を提示します。これらを提示した後に「病名」を提示する方が患者さんは理解しやすいと感じるでしょう。もしその病名に「一般名称」があるならば、それも追加するとよりわかりやすいでしょう。
「緊急性の説明」で役に立つ英語表現
緊急性を伝えるとき、多くの日本人医師が英語で直訳的に言ってしまいがちなのが “We must do the operation immediately or you may die.” のような表現です。
しかし must には「他の選択肢を認めない」という強い印象があり、さらに die という言葉は患者さんに過剰な恐怖を与え、「脅している」と受け取られる危険もあります。
そこでお勧めしたいのが下記のような「型」です。
This needs (治療・処置) now. We need to act quickly. Waiting could cause serious (harm damage complications). We’re not trying to scare you, but we do need to act quickly.
この need は must に比べて「他の選択肢も残されている」という柔らかい印象を与えますし、serious を使うことで die や death などを含む緊急性が十分に伝わります。また “We’re not trying to scare you” のように「脅すつもりはない」ということを明言することも有効です。
この「型」を使えば下記のような「緊急性の説明」が可能です。
This needs surgery now. We need to act quickly. Waiting could cause serious damage. We’re not trying to scare you, but we do need to act quickly.
この「型」を使った表現を用いれば、患者さんに恐怖心を与えすぎず、かつ緊急性を明確に伝えることもできるでしょう。
「治療の説明」で役に立つ英語表現
次に治療を説明する際に役に立つ「型」を外科的治療と内科的治療に分けてご紹介しましょう。
外科的治療に関する「型」
- • We’ll remove (病変部や原因となるもの) and repair (身体の機能や部位).
We’ll remove the damaged tissue and repair the area. - • We’ll fix (問題のある部位) so that (改善される機能).
We’ll fix the broken bone so that you can walk normally again. - • We’ll replace (病変部) with (人工物・正常なもの).
We’ll replace the cloudy lens with a clear artificial one. - • We’ll unblock (詰まっている部位) to restore (正常な機能).
We’ll unblock the artery to restore blood flow. - • We’ll repair (部位) and support (機能).
We’ll repair the hernia and support the muscle wall.
内科的治療に関する「型」
- • We’ll treat (原因・病変) to improve (症状・機能).
We’ll treat the infection to improve your fever and pain. - • We’ll remove (病変部) and prevent (再発・合併症).
We’ll remove the gallbladder and prevent more painful attacks. - • We’ll control (症状や病気) with (治療方法).
We’ll control your blood pressure with medication. - • We’ll support (機能や生活の質) by (治療・介入).
We’ll support your breathing by using inhalers.
ここでのポイントは remove や repair などのわかりやすい動詞を使うということです。上記のようにいくつかの「型」がありますので、これらを音読して身につけておいてください。
「リスクの説明」で役に立つ英語表現
Disclosureの説明の際に言及したように、リスクを英語で説明する際には「リスクの列挙は最小限に留めること」と「安心感を与える表現を加えること」が重要になります。
そこでお勧めしたいのが下記のような「型」です。
The main risks are (リスク), but serious problems are rare. Most patients recover well, and we’ll take steps to prevent complications.
The main risks are bleeding and infection, but serious problems are rare. Most patients recover well, and we’ll take steps to prevent complications.
このように 「リスク提示+安心感」 を組み合わせて説明することで、患者さんは過剰に不安になることなく、安心して同意に進むことができることでしょう。
理解を確認する teach back とは?
治療やリスクなどを説明した後には、患者さんがその内容を正しく理解できているかどうかを確認する必要があります。日本では「わかりましたか?」 “Does it make sense?” という質問に患者さんが「はい」と回答すれば「患者は理解した」と認識されますが、英語圏では teach-back method と呼ばれる手法がよく用いられます。
これは「医療者が説明した内容を患者自身の言葉で説明してもらう」という方法で、理解度の確認と同時に、説明が正しく伝わったかを確認することができます。
ここでは下記の2つの「型」を覚えておきましょう。
- • To make sure we’re on the same page, can you tell me in your own words what we just talked about?
on the same page という表現は「同じ認識を持つ」という意味で、患者さんと医療者が同じ理解を共有できているかを柔らかく確認するのに適しています。
- • Could you walk me through what you understood, so I can be sure I explained it clearly?
walk me through は「順を追って説明する」「一緒に確認する」というニュアンスを持ち、患者さんに負担をかけずに自然に理解を引き出すことができます。
このように teach-back の「型」を使えば、患者さんに「テストされている」と感じさせず、むしろ「医療者がきちんと説明できたかを確認している」と感じさせることができるのです。
患者が質問しやすくなる英語表現は?
最後に患者さんが質問しやすくなるような英語表現をご紹介しましょう。
よく “If you have any questions, please feel free to ask anytime.” という表現が使われますが、これは文法的には正しいものの、あまりに定型的で事務的な響きがあり、患者さんに「質問しづらい」と思わせてしまうことがあります。
患者さんに安心して質問してもらうためには、「質問はあるものだ」という前提で下記のような柔らかく促す表現を使うことが大切です。
- • Is there anything unclear?
- • Do you have any questions? It’s important you feel okay with this plan.
- • What’s on your mind right now?
- • I know this is a lot to take in, so please ask anything. There are no bad questions. We’re here to help you feel confident in the decision.
最後の「型」はやや長めですが、「質問をしてよい」と思える空気を強く後押しします。特に “There are no bad questions.” という表現は、臨床現場だけでなく学会などでも広く使える便利な表現です。
さてそろそろカップのコーヒーも残りわずかです。最後にもう一度 teach-back method で使える2つの「型」をお示しします。スラスラと言えるようになるまで何度も音読してくださいね。
- • To make sure we’re on the same page, can you tell me in your own words what we just talked about?
- • Could you walk me through what you understood, so I can be sure I explained it clearly?
では、またのご来店をお待ちしております。
「Dr. 押味の医学英語カフェ」では、読者の皆さまがこの連載で取り上げてほしい医学英語のトピックを募集しています。こちらのリンクよりご希望のトピックを自由に記載してお送りください。
国際医療福祉大学医学部 医学教育統括センター 教授
押味 貴之